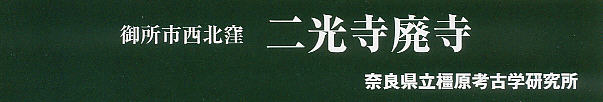
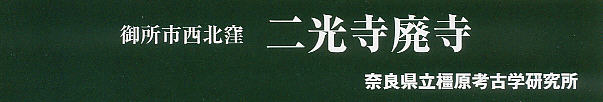
はじめに
この遺跡付近には、渡来系氏族の墓と考えられる北窪古墳群(6世紀後半)があり、南0.6kmには朝妻廃寺(渡来系氏族:朝妻氏の私寺)、南西2.5kmには高宮廃寺という古代寺院が知られています。今回の調査の結果、この地にも飛鳥時代の寺院が存在することを始めて確認しました。
調査地は御所市西北窪に位置し、小字が「二光寺」と地元で呼称されていることから、今回の発見した古代寺院を「二光寺廃寺」と命名しました。
遺構の概要
今回検出した主要な遺構は基壇建物です。しかし調査した範囲は、基壇建物全体の東半分です。出土遺物から見て飛鳥時代(7世紀後半)に創建され、平安時代のうちに倒壊し、鎌倉時代には耕作地となったことが分かりました。
基壇 「乱石積み二重基壇」と呼ばれる基壇です。上・下2段からなる基壇で、その周りには地元産の自然石を積み上げています。基壇の南北長は約17.2m以上あります。基壇上部は既に削平されていますが、南西端の礎石備え付け位置に残る根石(礎石の下に敷いた石)の状況から、基壇の高さは現状よりも約50cmは高いと(推定基壇高1m以上)と推測できます。
礎石 現在の基壇上には、南北に4列、東西に5列の礎石(地元産の1m前後の自然石)の大半が残されていますが、現状では礎石の高さが不揃いで、水平ではありません。これは耕作の邪魔になった際に、掘り返されて再び埋められたためです。しかし、各礎石の周りには当初の据付穴(直径2m弱)が残っており、現在の礎石位置は本来の位置とあまり変わっていないことが解りました。礎石は約3m間隔(中央の南北間は3m以上)に設置されていたと考えられます。
建物 基壇周囲から多量の瓦が出土し、この建物が瓦葺きと考えられること、專仏が数多く出土したこと、そして飛鳥時代の金堂の柱間は一般的に5間×4間であることから、この建物は寺院の中心的建物である金堂の可能性が最も高く、南を正面とする建物と考えられます。
遺物の概要
遺物には瓦・專仏・螺髪・鉄釘があり、基壇周囲(上層が瓦廃棄層、下層が瓦屋根倒壊層)から出土しました。
瓦 軒瓦には数種類ありますが、創建時の瓦と考えられるのは高宮廃寺、朝妻廃寺との同笵瓦(同じ型で作られた瓦)で、複弁蓮華紋軒丸瓦、偏向唐草紋軒平瓦です。他に重弧紋軒平瓦や少数ながら檜隈寺(明日香村所在)と同笵の複弁蓮華紋軒丸瓦も出土しました。


摶仏 これまでに4種類を確認しわずかに金箔の残るのもあります。大型多尊・方形三尊・方形六尊、そして方形十二尊連座と見られる摶仏です。大型多尊摶仏は唐招提寺(奈良市)所蔵例のほか、夏見廃寺(三重県)出土例などと細部までが酷似します。これには「甲午口五月中」という紀年銘があり西暦694年を指す可能性があります。方形六尊連立摶仏は朝妻廃寺と同範で、方形三尊摶仏は、現在のところ二光寺廃寺独自のものと見られます。








螺髪 土製の螺髪1点(高さ3.3cm、直径3.2cm)が出土しました。その大きさから、この建物内に高さ2mを越える塑像仏(丈六物)が安置されていたと考えられます。
まとめ
今回の大きな調査成果は2点挙げることができます。第一に、金剛山麓の当地に飛鳥時代(7世紀後半)の古代寺院を新しく発見したことです。出土した軒瓦には、朝妻廃寺・高宮廃寺との同笵瓦があり、同じ「金剛山麓の古代寺院」としての密接な関係を持っていたことが分かりました。北窪古墳群の存在を考慮すれば、二光寺廃寺の建立氏族として、当地に勢力を持っていた渡来系氏族の可能性などが考えられます。又檜隈寺との同笵瓦が出土したことも、建立氏族を考える上で重要な手掛りです。第二に、数多くの摶仏と螺髪が1点出土したことです。これらの出土によって、建物内部には丈六仏があり、壁は摶仏で装飾されていたという、仏教的な荘厳世界をより具体的に知ることが出来ました。以上のように、飛鳥時代の古代寺院と仏教を考古学的に考える上で、二光寺廃寺は全国的にも例の少ない貴重な古代寺院遺跡であるといえます。(広岡孝信)
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
二光寺廃寺跡
| 白鳳エキゾチック群像 御所でレリーフ出土 | |
御所(ごせ)市北窪で、7世紀末の古代寺院の金堂とみられる建物跡が出土し、一緒に仏像の土製レリーフ(仏(せんぶつ))の破片約200点が見つかった。いずれも白鳳美術の逸品で、これまで国内で出土例がない異国風の顔立ちの5人の群像もあり、細部までくっきりと残っていた。県立橿原考古学研究所が23日発表し、古い地名から「二光寺(にこうじ)廃寺」と名づけた。 |
|
未知の寺院からせん仏片−御所・二光寺廃寺
御所市西北窪で、飛鳥時代後半(7世紀後半)の寺院跡から約200点のせん仏片が見つかり、県立橿原考古学研究所が23日、発表した。金堂内を飾っていたとみられ、古代寺院の姿を知る重要な資料という。「二光寺廃寺」と命名された。
地下に埋もれた未知の寺院で、金堂基壇は南北約17メートル、東西約12メートル。見つかったのは東半分で、直径約1メートルの礎石が15個残っていた。本来は東西に長い建物だったと推定できる。
自然災害で倒壊したらしく、落ちて堆積(たいせき)した屋根瓦の間に多数のせん仏がはさまっていた。
一つのパーツに表された仏の数から、三尊、六尊連立、十二尊連坐、多尊の4種類が確認された。金ぱくが残る破片もあり、堂内を金色に飾っていたらしい。
現地説明会は26日午前9時半から午後4時。近鉄忍海駅から奈良交通の臨時バスが運行される。せん仏は同日午前9時から午後5時まで、同駅西側の葛城市歴史博物館で展示。(奈良新聞)
- 2月24日11時2分更新
二光寺廃寺 文献記録のない7世紀後半の寺を発掘 奈良
奈良県御所市西北窪で、文献に記録のない寺の金堂の礎石が見つかり、周囲から内部の壁を飾った「せん仏」(レリーフ状の型押しの仏像)の破片が大量に出土した。23日発表した県立橿原考古学研究所は、瓦などから7世紀後半のものとみており、地名から「二光寺廃寺」と命名した。
せん仏は、阿弥陀三尊の周りに僧や西域などの異国風の信者の群像を配した大型のものや、仏の姿を縦横にいくつも連ねたものなど4種類を確認した。
礎石は金堂の東半分のものとみられ、建物を復元すると南北約12.5メートル、東西約15メートル。10〜11世紀に自然倒壊したとみられる。近くに渡来系氏族の古墳群(6世紀後半)があり、この氏寺と考えられる。
せん仏の破片は約200点。阿弥陀三尊を中心とした大型多尊せん仏(復元すると約55センチ四方)は、夏見廃寺(三重県名張市)の出土例や唐招提寺(奈良市)の所蔵品と酷似しており、同じ工房で作られたと考えられる。金ぱくが残った破片もあり、金堂内をきらびやかに飾っていたとみられる。【中本泰代】(毎日新聞)
- 2月24日10時31分更新
飛鳥時代の廃寺からレリーフ状の仏像出土…奈良
|
奈良県御所市の寺院跡、二光寺(にこうじ)廃寺で、7世紀後半の粘土を焼いたレリーフ状の仏像「セン仏(せんぶつ)」の破片約200点が出土したと、県立橿原考古学研究所が23日、発表した。異国風の顔立ちをくっきりと刻んだものもあり、国際色豊かな白鳳美術を象徴する発見として注目される。
異国風の人物を刻んだセン仏の破片は、復元すると55センチ四方に達する大型のもの。中央にあったとみられる阿弥陀如来(あみだにょらい)を守る神将5体が刻まれ、端の跳ね上がった口ひげ、出っ張ったほお骨、太い鼻と大きな耳など、エキゾチックな顔立ちが確認できる。694年を示す「甲午」の文字が刻まれた破片もあり、このころ制作されたものとみられる。
肥田路美(ひだ・ろみ)・早稲田大教授(東洋美術史)は「顔つきはインド風に見えるが、唐や新羅の影響も感じられる。国際的な要素がぎっしり詰まっており、渡来系技術者が作ったのだろう」と推測している。(センは土ヘンに「専」の旧字体)(読売新聞)
- 2月23日22時59分更新
<二光寺廃寺>文献記録のない7世紀後半の寺を発掘 奈良
奈良県御所市西北窪で、文献に記録のない寺の金堂の礎石が見つかり、周囲から内部の壁を飾った「せん仏」(レリーフ状の型押しの仏像)の破片が大量に出土した。23日発表した県立橿原考古学研究所は、瓦などから7世紀後半のものとみており、地名から「二光寺廃寺」と命名した。
せん仏は、阿弥陀三尊の周りに僧や西域などの異国風の信者の群像を配した大型のものや、仏の姿を縦横にいくつも連ねたものなど4種類を確認した。
礎石は金堂の東半分のものとみられ、建物を復元すると南北約12.5メートル、東西約15メートル。10〜11世紀に自然倒壊したとみられる。近くに渡来系氏族の古墳群(6世紀後半)があり、この氏寺と考えられる。
せん仏の破片は約200点。阿弥陀三尊を中心とした大型多尊せん仏(復元すると約55センチ四方)は、夏見廃寺(三重県名張市)の出土例や唐招提寺(奈良市)の所蔵品と酷似しており、同じ工房で作られたと考えられる。金ぱくが残った破片もあり、金堂内をきらびやかに飾っていたとみられる。【中本泰代】(毎日新聞)
- 2月23日22時43分更新
<奈良>1300年前の仏のレリーフ見つかる
奈良県御所市で、飛鳥時代の寺院跡が見つかりました。そこから出てきたのが、仏をかたどった浮き彫りなどおよそ200点です。1300年以上前の美しい姿を今に伝える貴重な発見です。
穏やかな表情、衣の美しい曲線、そして足の指まで。微細なデザインが1300年前のものとは思えないほど、はっきりと見て取れます。これらの浮き彫りは、葛城山のふもと奈良県御所市の「二光寺廃寺」という、7世紀後半の寺院跡から見つかりました。今回確認されたのは、寺の金堂と見られる建物跡で、およそ200点も見つかった浮き彫りは、金堂の壁を飾っていたと考えられています。阿弥陀如来を中心とした大型の浮き彫りは、周囲には家来達が控え、その西域風の顔立ちは髭まで細かく描かれています。橿原考古学研究所の樋口隆康所長は「線がね、非常にシャープに細かく表現されてましてね、今まで見たせん仏(浮き彫り)の中では一番シャープな感じ」と話しています。
しかし、なぜ「1300年前」とはっきり分かったのでしょうか。それは、阿弥陀如来の台座に「甲午」という年号が記されていたからです。西暦で言えば694年。こういった浮き彫りは、渡来人たちの技術と言われています。渡来人の技術を用い、これほどの寺院を建てた人物とは。「当時の天皇家などとも関係が深かった人・・・まぁ葛城氏ということになるのかなぁ」と樋口所長。
葛城氏とは、大和政権で軍事・外交に大きな力を誇った豪族で、二光寺廃寺の周辺では葛城氏に関係する遺跡が多く見つかっています。遥か大陸からシルクロードで伝わった仏教美術が、1300年の時を経て現代に甦りました。葛城氏の権力の大きさを物語る、驚くべき発見です。
(朝日放送) - 2月23日19時29分更新
セン仏200点出土=7世紀末、金箔張りか−渡来系豪族の寺?・奈良
奈良県立橿原考古学研究所は23日、同県御所市西北窪で、7世紀後半の古代寺院の金堂とみられる遺構から、小型の仏像の型を粘土に押し付けて焼き上げた※仏(せんぶつ)の破片約200点が出土したと発表した。今回の出土量は、夏見廃寺(三重県名張市)の約500点などに次ぐ多さ。金堂内部の壁を飾っていたとみられ、同研究所はこの寺院を二光寺廃寺と名付けた(※=土へんに專)。
最大のものは1辺約55センチのほぼ正方形で、多くの仏像が浮き彫りにされている。この隅に694年を指す「甲午」という文字があることから、7世紀末の制作とみられる。このほか仏像が3体並ぶものや6体浮き彫りにされたものなど計4種類出土。二光寺廃寺の南600メートルに位置する朝妻廃寺、夏見廃寺などから出土した※仏とよく似た特徴を示している。金箔(きんぱく)や漆が残っていたものがあることから、表面には金箔が張られていた可能性が高い。 (時事通信)
- 2月23日18時1分更新
|
国際派?「白鳳五人仏」/二光寺 |
|
|
エキゾチックな顔立ちは、どこの国の人? 奈良県御所市の二光寺廃寺で見つかった白鳳時代の仏像の土製レリーフ(仏(せんぶつ))は、近畿を中心に全国で出土例は100前後。その中でも今回の像は保存状態が良く、表情や衣装の鮮明さは際だっている。特に、インドやペルシャの人を思わせる群像に専門家は目を見張る。7世紀末に粘土で作られた小さな仏から、当時の国際交流や美術界への想像が膨らむ。
|
|
|
( |